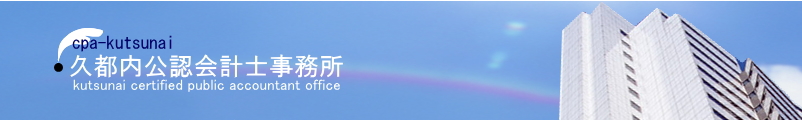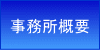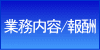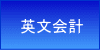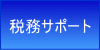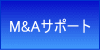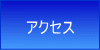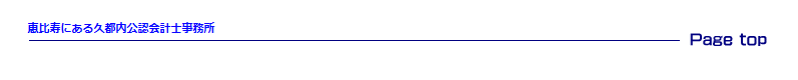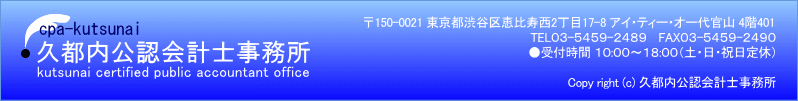| |
|
|
 |
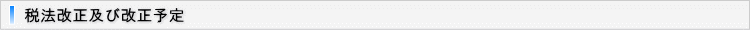
| |
税法改正資料(2025 年版)
2025 年 6 月
今回の改正はパートタイマー等給与収入についての非課税金額 103 万円についての見直しが中心話題でした。
その他最近の改正で実務上参考となる点等を記載させていただきます。
〔1〕 個人所得税
(1) 給料の非課税金額が 103 万円から 160 万円へ
今迄所得税 0 となる給与収入は 103 万円以下でしたが、改正後は給与収入 160 万円以下となります。
⇒令和 7 年以降恒久的に適用されます。
(2) 給料 200 万円以下の改正
今まで基礎控除 48 万円が 95 万円になります。
⇒令和 7 年以降恒久的に適用されます。
(3) 給料 200 万円超 2,545 万円以下の改正
|
|
改正前の基礎控除 |
改正後の基礎控除 |
| 給料 200 万円超 475 万円以下 |
48 万円 |
88 万円 |
| 給料 475 万円超 665 万円以下 |
48 万円 |
68 万円 |
| 給料 665 万円超 850 万円以下 |
48 万円 |
63 万円 |
|
|
⇒令和 7 年分及び令和 8 年分の時限措置で令和 9 年分以後の基礎控除は 58 万円になります。
(4) 特定親族特別控除の創設
現在の人手不足に対応するため大学生のアルバイトを増やす目的で創設されました。
個人が生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等の合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下の
場合特定親族特別控除の対象となりその個人のその年分の総所得金額等から次の通り控除することと
なります。
なお合計所得金額が 58 万円以下の場合は、特定扶養親族の控除の対象となり 63 万円を控除するこ
ととなります。ただし配偶者及び青色事業専従者等を除きます。
この創設で大学生がアルバイトすることで親の扶養控除から外れてもこの特別控除の可能性があるこ
とになります。令和 7 年分から適用になります。
|
|
| 親族等の合計所得金額 |
控除額 |
| 58 万円超 85 万円以下 |
63 万円 |
| 85 万円超 90 万円以下 |
61 万円 |
| 90 万円超 95 万円以下 |
51 万円 |
| 95 万円超 100 万円以下 |
41 万円 |
| 100 万円超 105 万円以下 |
31 万円 |
| 105 万円超 110 万円以下 |
21 万円 |
| 110 万円超 115 万円以下 |
11 万円 |
| 115 万円超 120 万円以下 |
6 万円 |
| 120 万円超 123 万円以下 |
3 万円 |
|
|
(5) 生命保険料控除の改正
子育て世帯への支援の一環として、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額が見直されま
す。23 歳未満の扶養親族を有する場合は、一般生命保険料控除の控除額が最大 6 万円に引き上げられ
ます。なお合計限度額は 12 万円で変わりません。
改正後における新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額
| |
|
|
| 23歳未満の扶養親族を有する場合 |
左記以外の場合 (現行と同様) |
| 年間の新生命保険料 |
控除額 |
年間の新生命保険料 |
控除額 |
| 3万円以下 |
新生命保険料の全額 |
2万円以下 |
新生命保険料の全額 |
| 3万円超 6万円以下 |
新生命保険料×1/2
+1万5千円 |
2万円超 4万円以下 |
新生命保険料×1/2
+1万円 |
| 6万円超 12万円以下 |
新生命保険料×1/4
+3万円 |
4万円超 8万円以下 |
新生命保険料×1/4
+2万円 |
| 12万円超 |
一律 6万円 |
8万円超 |
一律 4万円 |
|
|
令和8年分に限り適用されます。
〔2〕 法人税
(1) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業向け賃上げ促進税制)
① 適用年度⇒令和 6 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
② 税額控除限度額の計算式
A) 給与等支給増加割合 1.5%以上⇒増加額の 15%
B) 給与等支給増加割合 2.5%以上⇒増加額の 30%
C) 教育訓練費の増加割合 5%以上かつ教育訓練費の額が給与等支給の 0.05%以上⇒増加額の 10%
D) くるみん認定若しくはえるぼし認定を受けた場合⇒増加額の 5%
E) 法人税額の 20%が限度
③ 役員、使用人兼務役員及び役員の親族関係者を除く国内雇用者に対する給与が対象。アルバイトなど雇
用保険対象に該当しない者も含まれます。
④ 5 年間繰り越して税額控除できますので、青色申告法人で従業員給与が前年度より 1.5%増加した場合
たとえ赤字でも必ず別表六(二十四)及び別表六(二十四)付表一を申告書に含めて提出してください。
⑤ 当初申告要件が付されていますので、当初の確定申告の際に上記各別表を添付していなければなりま
せん。
⑥ 5 年間の繰越控除制度を利用する場合は、当初の繰越年度から連続して青色申告書を提出し、上記各別
表を添付していなければなりません。
(2) 防衛特別法人税
① 適用年度⇒令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する各事業年度に適用されます。
② 税額の計算式
(法人税-500 万円)×4%=防衛特別法人税
③ たとえ税額が無くても防衛特別法人税申告書を提出する必要があります。
(3) 交際費
① 期末資本金の額又は出資金の額が 1 億円以上(資本金の額又は出資金の額が 5 億円以上である法人に
よる完全支配関係がある法人等を除く)は次のいずれかを選択して計算した金額が損金不算入額となります。
イ) その事業年度において支出する交際費等の額-(接待飲食費の額×50%)
ロ) その事業年度において支出する交際費等の額-800 万円
(注)接待飲食費は当法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを
除きます。
② 接待に関連しての送迎費は交際費に該当します。ただし他社が主催する懇親会に当社の役員を出席さ
せるために要するタクシー代は、交際費以外の単純損金(旅費交通費)になります。
③ 1 人当たり 10,000 円以下(令和 6 年 4 月 1 日前に支出した飲食費については 5,000 円以下)の飲食費
で帳簿書類に次の事項を記載している場合は交際費から除外できます。
イ) 飲食等のあった日
ロ) 飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
ハ) 飲食費の額並びに飲食店等の名称及びその所在地
ニ) 飲食費に係る飲食等に参加した者の数
ホ) その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
④ 会議費等は、1 人当たり 10,000 円を超える場合であっても交際費には該当しません。
⑤ 税抜経理方式を適用している法人は、交際費等に係る消費税等の額のうち控除対象外消費税額等に相
当する金額を交際費等の額に含めて損金不算入額を計算する必要があります。
(4) 少額減価償却資産の損金算入特例
① 青色申告の中小企業等が取得価額 30 万円未満の少額減価償却資産を取得等をし、事業の用に供した場
合に損金経理を要件に、その全額を損金算入できます。
② 大規模法人の子会社等を除きます。
③ 年 300 万円が限度です。
④ 事業年度終了の日において、常時使用する従業員の数が 500 人以下であることが要件です。
⑤ 令和 4 年 4 月 1 日以後の取得等については、貸付け(主要な事業として行われる貸付けを除く)の用
に供した資産は除外されています。
⑥ 適用期間は令和 8 年 3 月 31 日まで取得したものです。
(5) 税務調査のポイント
税務調査では、売上と売上原価が最大のポイントになります。特に期末直前の仕入、外注費、翌期
首直後の売上について期末棚卸資産に計上されているかどうか等がマークされます。
経費については、事業遂行上の費用であることを明確に説明できることが必要です。
〔3〕 消費税
令和 5 年 10 月 1 日からインボイス制度がスタートして 1 年半以上になりますが、もう一度整理してみ
たいと思います。
(1) 少額な返還インボイスの交付義務免除(対象:全事業者・恒久措置)
① 返品や値引き等の額が税込価額 1 万円未満の場合→返還インボイスの交付義務なし
② 返品や値引き等の額が税込価額 1 万円以上の場合→返還インボイスの交付義務あり
(2) 2 割特例(対象:小規模事業者・3 年間の時限措置)
① 基準期間の課税売上高が 1,000 万円未満の免税事業者がインボイス登録している場合は消費税の納税額
を課税売上高の 2 割とする特例
② 適用対象期間は令和 5 年 10 月 1 日から令和 8 年 9 月 30 日までの日の属する各課税期間
③ 3 年間の特例期間が終了した後簡易課税制度を選択したい場合は特例期間終了後の翌課税期間中に「簡
易課税制度選択届出書」を税務署に提出すれば適用できます。
(3) 少額特例(対象:課税売上高 1 億円以下の事業者・6 年間の時限措置)
① 基準期間における課税売上高が 1 億円以下又は特定期間の課税売上高が 5,000 万円以下である事業者
については、支払対価の額が 1 万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみ
の保存で仕入税額控除が可能とされています。なお支払対価の額が 1 万円未満か否かは 1 取引単位で判
定します。
特定期間は前年又は前事業年度開始の日以後 6 ヵ月の期間をいいます。
② 対象期間は令和 5 年 10 月 1 日から令和 11 年 9 月 30 日の間です。
(4) 不動産賃貸の貸主が返還しない保証金は契約時等にインボイス交付
① 契約書に保証金の一定金額を償却額として返還しない旨定められている場合貸主の課税売上げ、借主の
課税仕入れに計上することになります。従って貸主はインボイスを交付する義務が生じ、借主は貸主か
らインボイスの交付を受け保存することが必要です。
(5) 免税事業者からの課税仕入れの処理(税抜き処理のケース)
① 令和 5 年 10 月 1 日~令和 8 年 9 月 30 日
イ) 仕入税額とみなされる金額(仕入税額相当額の 80%)→仮払消費税
ロ) 仕入税額控除の対象外 20%→対価の額(本体価格)に含める
② 令和 8 年 10 月 1 日~令和 11 年 9 月 30 日
イ) 仕入税額とみなされる金額(仕入税額相当額の 50%)→仮払消費税
ロ) 仕入税額控除の対象外 50%→対価の額(本体価格)に含める
③ 令和 11 年 10 月 1 日~
イ) 仕入税額控除の対象外 100%→対価の額(本体価格)に含める
(6) 相続があった場合におけるインボイス制度下の留意点
① 課税事業者である個人事業者が死亡した場合には、相続人は「個人事業者の死亡届出書」を速やかに被
相続人の納税地の税務署に提出しなければなりませんが、被相続人がインボイス発行事業者である場合
には、これに代えて「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出しなければなりません。
そして、その相続人(インボイス発行事業者を除きます)がインボイス発行事業者である被相続人の
事業を承継する場合には、その届出書にその旨を記載することとされています。
② 事業を承継した相続人がインボイス発行事業者でなかった場合には、その相続人が被相続人の死亡後も
途切れることなくインボイスを交付することができるようにするためには、死亡した日の翌月から 4 月
以内にインボイスの登録をする必要があります。
(7) 出張旅費特例
① 社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額
については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が適用できます。
(8) 事務所賃貸料のインボイス交付方法
事務所や店舗の賃貸をしている場合の毎月の家賃についてのインボイスの交付方法は次の様になります。
① 賃貸料を受け取る度にインボイスを交付する。
② 一定期間(暦年や賃借人の事業年度等)に支払を受けた賃貸料合計額を記載したインボイスを交付する。
③ 賃借人が作成したインボイスの記載事項を満たす仕入明細書の記載事項を確認する。
④ 賃借人に登録番号を通知し、契約書と支払年月日の分かる通帳や振込金受取書とともに保存するように
連絡する。
※不動産管理会社に交付に係る事務を委託することもできます。
(9) ETC 利用証明書の取得とインボイス
① ETC クレジットカードの高速道路利用料金(ETC 料金)に仕入税額控除を適用するには原則、簡易イ
ンボイスとしてその全ての ETC 利用に係る「利用証明書」を「ETC 利用照会サービス」でダウンロー
ドして取得・保存する必要があります。
② ただし ETC の利用に係るクレジットカード会社の「クレジットカード利用明細書」の保存を条件に「利
用証明書」は利用した高速道路会社等につき任意の 1 回分を取得し保存すれば仕入税額控除が
認められます。
③ 任意の 1 回分の取得頻度については毎月、毎年など一定期間ごとに 1 回ではなく、利用した高速道路会
社等の「利用証明書」を文字通り 1 回のみ取得するだけで済みます。
(10)輸入取引において課税された消費税額の控除対象
① 輸入取引についてはインボイスの保存を要件とするものではなく税関⾧から交付を受けた輸入許可書
を保存することにより税額控除の対象とすることができます。
② 従って輸入取引に係る仕入税額控除は、税関⾧から交付を受けた輸入許可書に記載の税額に基づき税額
控除をすることとなります。
〔4〕 相続税、贈与税
令和 6 年 1 月 1 日以後の抜本的改正について記載した他一般的な節税方法及び当事務所が相続税申告
業務で心掛けていることも記載しております。
(1) 暦年贈与の今迄の制度
① 贈与税は暦年贈与に関する贈与税と相続時精算課税に関する贈与税があります。
② 相続時精算課税の届出をしなければ一般的な贈与は暦年贈与となります。
③ 暦年贈与では 110 万円の基礎控除までは、贈与税がかかりませんが、贈与が 110 万円を超えた場合は
超過分について翌年 3 月 15 日までに贈与税の申告納税を税務署に対してする必要があります。
④ 今迄は相続税の申告について相続開始日から遡って 3 年間分の暦年贈与(110 万円未満の贈与も含めて)
を相続財産にプラスすることになっていました。
⑤ 納めた贈与税があれば相続税からマイナスします。
(2) 暦年贈与の税率(一般税率)
|
|
200 万円以下
200 万円超 300 万円以下
300 万円超 400 万円以下
400 万円超 600 万円以下 |
10%
15%
20%
30% |
600 万円超 1,000 万円以下
1,000 万円超 1,500 万円以下
1,500 万円超 3,000 万円以下
3,000 万円超 |
40%
45%
50%
55% |
|
(3) 暦年贈与の税率(特例税率)
父母、祖父母、養父母等直系尊属からの贈与により財産を取得した受贈者(ただし、その年の 1 月 1 日
において 18 歳以上の者に限ります。)については下記の「特例税率」を適用して贈与税を計算します。
|
|
200 万円以下
200 万円超 400 万円以下
400 万円超 600 万円以下
600 万円超 1,000 万円以下 |
10%
15%
20%
30% |
1,000 万円超 1,500 万円以下
1,500 万円超 3,000 万円以下
3,000 万円超 4,500 万円以下
4,500 万円超 |
40%
45%
50%
55% |
|
(4) 暦年贈与の改正点
遡って相続財産にプラスする暦年贈与の対象期間が次の様に改正されました。
|
|
| 贈与者の相続開始日 |
遡って相続財産にプラスする期間 |
| 令和 6 年 1 月 1 日~令和 8 年 12 月 31 日 |
相続開始前 3 年間 |
| 令和 9 年 1 月 1 日~令和 12 年 12 月 31 日 |
令和 6 年 1 月 1 日~相続開始日 |
| 令和 13 年 1 月 1 日~ |
相続開始前 7 年間 |
|
|
なお令和 6 年 1 月 1 日以後に贈与により取得する財産について、相続財産にプラスする贈与財産の価額
は遡って 3 年間の贈与された財産以外の財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額となります。
(5) 当事務所の対応
今迄当事務所に相続税申告をご依頼された場合贈与の申告洩れ防止のため相続から遡って3 年分の
被相続人の通帳コピーをいただいておりましたが、今後は税務署の指摘を受けないため遡って被相続人の
通帳コピーをいただく期間は改正に伴って最大 7 年間までに増大致します。
(6) 相続時精算課税の今迄の制度
① この制度を適用するためには受贈者が税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要が
あります。
② 受贈者は贈与を受けた年の 1 月 1 日において 18 歳以上、贈与者は贈与をした年の 1 月 1 日において
60歳以上である者が必要です。
③ 受贈者が各々、贈与者ごとに適用を受けることができ、一度この制度の適用を受けた場合には暦年課税
への変更はできません。
④ 贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から 2,500 万円までの特別控除額を控除した金額に一律 20%
の税率を乗じて算出します。
⑤ 相続時精算課税の制度で贈与した金額は相続の時全額を相続財産にプラスします。
(7) 相続時精算課税の改正点
① 「相続時精算課税選択届出書」を提出していれば年間 110 万円までの贈与については申告納税が不要で
す。又贈与税の額は、贈与者ごとの贈与財産の価額の合計額から基礎控除額 110 万円を控除した後、
2,500 万円までの特別控除額を控除した金額に一律 20%の税率を乗じて算出します。
② 相続時に相続税の課税価格にプラスする財産の価額は基礎控除額を控除した後の残額です。
③ 令和 6 年 1 月 1 日以後の贈与に適用されます。
④ 2 人以上から贈与を受けた際の基礎控除 110 万円の計算は次の様になります。
父 300 万円、母 200 万円の金銭等の贈与を受けた場合
イ) 父の按分後の基礎控除額
110 万円×300 万円/500 万円=66 万円
ロ) 母の按分後の基礎控除額
110 万円×200 万円/500 万円=44 万円
⑤ 相続時精算課税を選択したら贈与の翌年 3 月 15 日まで申告する必要があります。
(8) 相続税の節税方法
① 相続時精算課税制度で基礎控除 110 万円について相続財産から除いて相続税の計算ができる様になり
ましたので、これを利用して⾧期的に行なっていくことが、相続税減少につながることになります。
② 女性の方が⾧生きするケースが多いので、父からの贈与は相続時精算課税贈与、母からの贈与は暦年贈
与にすると 110 万円の控除をダブルで使えます。
③ 将来的に値上がりが見込める土地について相続時精算課税贈与をすれば贈与時は 2,500 万円の特別控
除額を差し引いて残額の 20%の税金を納付すれば良く、相続の時は相続時の評価ではなく、贈与時の
評価での課税価格になりますので、節税になります。
④ 暦年贈与が今後 7 年遡って相続税の対象になるところからその対象者以外の孫や、子供の配偶者へ亡く
なる直前に贈与を行なっても相続税は課税されません。ただし相続財産の分配があった場合は贈与分も
加えて相続税の対象となりますので注意してください。
⑤ 令和 6 年 1 月 1 日から令和 8 年 12 月 31 日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等
資金のうち一定の金額について贈与税が非課税になります。
一定金額は一般住宅 500 万円、省エネ等住宅 1,000 万円です。
受贈者の要件
イ) 贈与を受けた時に住所を有し、かつ日本国籍を有する者
ロ) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
(直系卑属とは自分からみて下の世代で直通する血縁関係にある親族を指します。具体的には子、孫、
ひ孫など自分より後の世代の人が含まれます。また養子も直系卑属となります。)
ハ) 贈与を受けた年の 1 月 1 日において 18 歳以上であること
ニ) 贈与を受けた年分の合計所得金額が 2,000 万円以下(新築、取得又は増改築等をする住宅用の家屋
の床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満の場合は 1,000 万円以下)であること
ホ) 贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若し
くは取得又は増改築等をすること
※「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅用の家
屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み「住宅用の家屋の取得
又は増改築等」には、その住宅用の家屋の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地
等の取得を含みます。
ヘ) 贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日までに、その家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に
居住することが確実であると見込まれること
ト) 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある者から住宅用の家屋を取得したものではない
こと、又はこれらの者との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
チ) 平成 21 年以降の贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用
を受けたことがないこと
⑥ 小規模宅地等の特例を 1 次相続の他 2 次相続でも使うことを考えてみることも有効かと思います。
⑦ 現金を不動産に変えることで評価額が低くなりますので検討してみるのも良いと思います。
⑧ 孫を養子にする方法もあります。税額を低くするための養子の数は実の子供がいる場合は 1 人、実の子
供がいない場合は 2 人です。
・当事務所の相続税申告業務の方針
① 節税を考慮しながら 2 次相続及び相続人間の公平性に留意して総合的に最良の方法を相続人と一緒に
考えていきます。
② 相続財産に土地が含まれている場合、土地の評価減で大きく相続税を減らすことができる場合がありま
すので、現地視察をし、区役所等で調査し、評価減の余地がないか十分検討致します。
③ 相続に関連する資料を全て添付し、必要な場合は説明メモも添付して提出することで、税務調査の可能
性を減らしています。
〔5〕 国際課税
一般的な抜本的改正はありませんので、実務で役立ちそうな点をいくつか記載させていただきます。
(1) 外国税額控除⇒法人での外国税額控除について
① 外国税額控除とは、国際的な二重課税を排除するために、海外で納付した(源泉徴収された)外国法人
税を一定の条件のもと日本の法人税等から差し引く制度をいいます。
② 実際に入金を受けるまでは外国税額控除の適用を受けられません。
③ 入金元から送られてくるタックス・レシート(源泉徴収票や納税証明書等)と仕訳の照合を行うことに
なりますので、できるだけ早期にタックス・レシートを送ってきてくれるように依頼する必要があります。
④ 外国法人税から控除対象外の税金を差し引きます。
必ず租税条約における限度税率のチェックを行なう必要があります。
例えば、入金元である A 国の国内法における源泉税率が 20%、日本と A 国の租税条約における限度
税率が 10%とすると、仮に入金元が 20%の源泉税率を適用してきたとしても、外国税額控除の対象と
なるのは 10%部分だけということです。
⑤ 控除限度額の算式
法人税の控除限度額=法人税額×調整国外所得金額/所得金額(全世界所得)
「調整国外所得金額」とは、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しなどの一定の規定を適用
しないで計算した場合の「国外所得金額」をいい「計算結果>所得金額×90%」となる場合には、
「所得金額×90%」が調整国外所得金額となります。
⑥ 控除税額の計算
控除対象外国法人税の額は、まず法人税の控除限度額の枠内で法人税の額から控除され、控除しきれ
ない場合、次に地方法人税の控除限度額の枠内で地方法人税の額から控除され、それでも控除しきれな
い場合、住民税の控除限度額の枠内で住民税の額(道府県民税の額及び市町村民税の額)から控除され
ます。つまり控除の順序としては、「法人税→地方法人税→住民税(道府県民税→市町村民税)」となり
ます。
⑦ 繰越しについて
控除対象外国法人税額が控除限度額(地方法人税及び住民税の控除限度額を含む)を上回るときのそ
の超過額、また逆に控除限度額を下回るときのその余裕額は、ともに将来 3 年にわたり繰越しが可能で
す。ただし、地方法人税について控除余裕額の繰越制度はありません)。
これは、控除限度額計算のベースとなる国外所得の発生時期と、それに対して外国法人税が課される
時期が必ずしも一致しないことへの配慮といえます。
(2) 非永住者及び非居住者等個人の申告に関する事項
① 非永住者とは居住者のうち日本国籍を有しない個人で、過去 10 年以内に国内に住所又は居所を有して
いた期間の合計が 5 年以下である個人をいいます。
② 永住者は全ての所得が課税対象となるのに対して、非永住者は非国外源泉所得の他、国外源泉所得で国
内において支払われたもの又は国内に送金されたものが課税対象になります。
多額の自己資金(例えば、住宅の購入資金など)を国内に送金すると、国外払いの国外源泉所得の送
金があったものとして課税される場合がある点に留意する必要があります。
③ 居住者は非永住者を除き国内・国外源泉所得の全ての所得が課税対象となるのに対し、非居住者は国内
源泉所得について課税対象となりますので、国外源泉所得は非課税となります。
④ 近年、非居住者として課税されていた個人が税務調査により居住者と認定され課税を受けるケースが増
えています。
居住者とは国内に生活の拠地があるか、本拠地が無い場合でも 1 年以上継続して居住している場合を
いいますが、その場所が生活の本拠地であるか否かは以下の様な実態を総合勘案して判定することとさ
れています。
(住所の判定要素となる実態)
・住居の所在
・職業(勤務先はどこかなど)
・生計を一にする配偶者親族の所在
・保有する資産の所在
・国内における滞在日数
・住民票等の登録場所
⑤ 非居住者は国内源泉所得に対して課税されますが、給与・報酬などの役務提供所得の国内源泉所得は、
原則的にその給与・報酬などの支払者に関わらず国内勤務期間に基づき計算されるため、国外から出張
などで来日する場合であっても各租税条約に規定される短期滞在者免税に該当しない場合には、所得税
の課税が生じます。
⑥ 居住者で、その年の 12 月 31 日において、その価額の合計額が 5,000 万円を超える国外財産を有する場
合には、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年 6
月 30 日までに提出しなければなりませんが、非永住者は除かれています。
⑦ 所得金額が 2,000 万円を超え、かつ、その年の 12 月 31 日において、その価額の合計額が 3 億円以上の
財産又はその価額の合計額が 1 億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合には、その財産の種類、
数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書をその年の翌年の 6 月 30 日
までに提出しなければなりません。
⑧ 所得金額の要件に関わりなく、12 月末の財産の額が 10 億円を超えていれば財産債務調書の提出義務が
あります。又財産債務調書は国外財産調書と異なり、非永住者であっても提出義務があるため、本国に
多額の財産を保有している者は、国外財産調書の提出義務がない場合であっても、その所得金額に関わ
りなく財産債務調書により国外財産の明細を提出する義務が生じることになるので、この点に留意する
必要があります。
(3) 消費税の国際課税
① 内外判定基準
イ) 有形資産
譲渡又は貸付けが行われる時の資産の所在地国
ロ) 登録で生じる無形資産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等
登録機関の所在地国
2 カ国以上で登録している場合は権利の譲渡・貸付けを行う者の住所地
ハ) 創作で自動的に生じる無形資産(著作権、ノウハウ等)
権利の譲渡・貸付けを行う者の住所地
ニ) 提供地が明らかな役務の提供
役務の提供が行われた場所
ホ) 提供地が明らかではない場合等の役務の提供
役務提供を行う者の、その役務提供に係る事務所等の所在地
ヘ) 電気通信利用役務
電気通信利用役務の提供を受ける者の住所又は本店の所在地等
② 輸出免税
無形資産と役務提供に係る輸出免税は、まずその取引が内外判定で国内取引に該当することが前提で
その上で取引相手が「非居住者」である場合に適用されます。
税関を通るという要件に代えて、非居住者に対する譲渡等という要件を満たすことで、国外で消費が
行われるものと考えるわけです。
例えば、特許庁に登録している特許の使用許諾をしてロイヤリティを受け取ることは国内(課税)取
引になりますが、その相手が非居住者であれば輸出免税になるということです。また国内で行う情報収
集という役務提供は内外判定で国内取引になりますが、その結果を提供する相手が非居住者であれば、
対価は輸出免税になります。
なお、ここでの「非居住者」は所得税法上の非居住者ではなく、「外国為替及び外国貿易法」に定義
される非居住者です。この法律で非居住者は居住者以外の自然人及び法人をいいますが居住者は本邦内
に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支
店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とに関わらず、その主たる事務所が外国にある
場合においても居住者とみなす。
以上所得税の定義と少々異なる場合もありますが、基本的な考え方(日本に住所や本店登記を有して
いない)はおおむね同じです。従って、無形資産や役務提供取引に対する輸出免税の判定においては、
まずその取引が内外判定で国内取引かどうか、次に取引相手が非居住者であるかどうかの確認がポイン
トになります。
③ 輸入消費税
輸入消費税は税関に納付した消費税です。
税関を通って輸入される貨物は、税関に消費税を納付しないと保税地域から引き取れません。これに対
して、税関を通らない無形資産や役務提供の輸入には、輸入消費税を課税する規定がありません。
④ 電気通信利用役務の提供に係る課税
イ) リバース・チャージ方式
国外事業者から受ける「事業者向け」の電気通信利用役務の提供については、国外事業者が支払
うべき消費税をサービスの買手(対価の支払者)自身が申告納税し、国外事業者には税抜価格を支
払うというものです。
⇒適用しない事業者
・免税事業者
・課税売上割合が 95%以上である事業者
・簡易課税を適用する事業者
ロ) 令和 7 年 4 年 1 日から適用される「プラットフォーム課税」
国外事業者が行う「消費者向け」の電気通信利用役務の提供のうち「特定プラットフォーム事業
者」を介して決済まで行われる役務提供については、国外事業者ではなく特定プラットフォーム事
業者が行ったものとみなして、国外事業者に代わって消費税を申告納税する仕組みです。
(4) 源泉所得税の国際課税
① 非居住者が国内及び国外の双方にわたって行った勤務又は人的役務の提供に基因して給与又は報酬の
支払を受ける場合におけるその給与又は報酬の総額のうち、国内において行った勤務又は人的役務の提
供に係る部分の金額は、国内における公演等の回数、収入金額等の状況に照らしその給与又は報酬の総
額に対する金額が著しく少額であると認められる場合を除き、次の算式により計算するとされています。
給与又は報酬の総額×国内において行った勤務又は人的役務の提供の期間/給与又は報酬の総額の
計算の基礎となった期間
(注)国内において勤務し又は人的役務を提供したことにより特に給与又は報酬の額が加算されている場合等に
は、上記算式は適用しません。
② 役務に関する特例
役員報酬については、勤務地に関わらず、法人の所在地国(内国法人の場合は日本)で生じたものと
されます。
③ 短期滞在者の免税
イ) 滞在期間が課税年度又は継続する 12 ヵ月を通じて合計 183 日を超えないこと。
ロ) 報酬を支払う雇用者は、勤務が行われた締約国の居住者(法人を含みます)でないこと。
ハ) 給与等の報酬が、役務提供地にある支店その他の恒久的施設によって負担(課税所得の計算上損金
に算入)されないこと。
④ 使用料関連の国内源泉所得として源泉徴収が必要
イ) 土地等の譲渡対価 10.21%
国内にある次に掲げる土地等の譲渡対価のうち、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供
するために譲り受けた個人から支払われるもの(譲渡対価が 1 億円を超えるものを除きます)以外
のもの
・土地又は土地の上に存する権利
・建物及び建物の附属設備
・構築物
ロ) 不動産の賃貸料 20.42%
国内にある不動産、不動産の上に存する権利若しくは採石権の貸付け、租鉱権の設定又は居住者
若しくは内国法人に対する船舶・航空機の貸付けによる対価
ハ) 貸付金の利子 10%(租税条約による限度税率)
国内において業務を行う者に対する貸付金で、その業務に係るものの利子
ニ) 使用料等 10%(租税条約による限度税率)等
国内において業務を行う者から受ける次の使用料又は対価で、その業務に係るもの
・工業所有権等の使用料又はその譲渡による対価
・著作権等の使用料又はその譲渡による対価
・機械、装置及び車両等の使用料
⑤ 課税漏れとなりやすい国内源泉所得として源泉徴収
イ) 人的役務提供事業
・海外の芸能プロダクションに対する人的役務提供事業の対価
・外国人ミュージシャン、スポーツ選手等に対する報酬
ロ) 給与等
・非居住者である役員に対する給与
・海外出向者に対する出国後賞与の国内源泉所得分
・非居住者である外国人労働者に支払った給与
ハ) 使用料
・非居住者等に支払った著作権や特許権の使用料等
・ソフトウェアの開発費、使用料
・インド法人に支払った技術上の役務に対する料金
・美術品等の使用料
ニ) 不動産譲渡等
・非居住者等に支払った土地等の譲渡対価
・非居住者等に支払った不動産賃借料
ホ) 利子・配当
・外国法人に支払った借入金利子、配当
(5) 事業所得と雑所得
① 事業所得の場合青色申告承認申請することで青色申告に関連する様々な特典が得られ、又損失が生じた
場合は損益通算ができます。
② 雑所得は青色申告の対象にはならず又損失が生じても他の所得と損益通算はできません。
③ 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度
で行っているかどうかで判定します。
ただし、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が 300
万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除きます)には、業務に係る雑所得に該当し
ます。
④ その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事実と
認められるかどうかを個別に判断することとなります。
イ) その所得の収入金額が僅少と認められる場合…例えば、その所得の収入金額が、例年 300 万円以下
で主たる収入に対する割合が 10%未満の場合は「僅少と認める場合」に該当するとされています。
(注)「例年」とは概ね 3 年程度の期間をいいます。
ロ) その所得を得る活動に営利性が認められない場合…その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消する
ための取組を実施していない場合は「営利性が認められない場合」に該当するとされています。
(注)「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字に
するための営業活動を実施していない場合をいいます。
ハ) 帳簿の記録、保存していない場合は、一般的に営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め
難く、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと取り扱うこととさ
れています。
ニ) ただし、その所得を得るための活動が、収入金額 300 万円を超えるような規模で行っている場合に
は、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず事業所得と認められる事実がある場合
には、事業所得と取り扱うこととされています。
以上ご参考になれば幸いに存じます。
|
|
|
 |
|
|
|